Zenkoku Nichirenshu Seinennkai

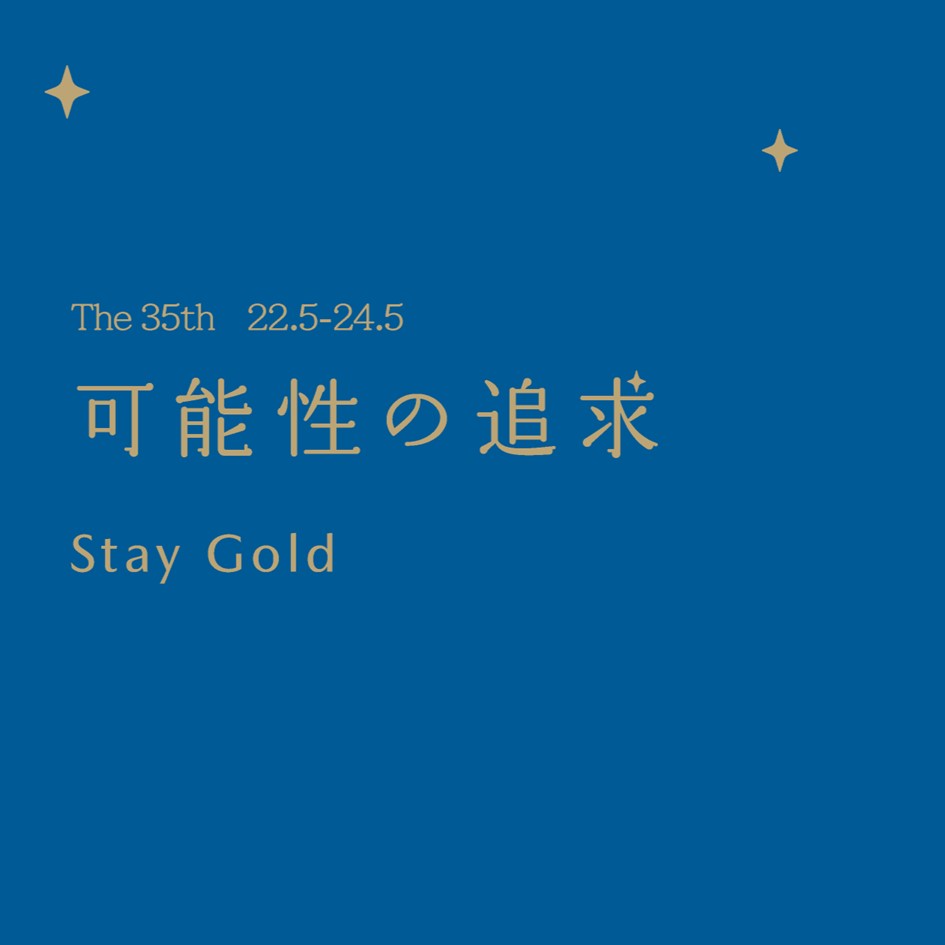
概要
全日青とは、北海道・東北・関東・山静・北陸・中部・近畿・中四国・九州ブロックに分けられた各単位日青会(参画59団体、総会員数約1000名/令和2年5月現在)および、海外の2団体の青年僧が参加し、宗祖日蓮大聖人の願いである「立正平和」「立正安国」を目指した活動を展開している団体です。
トピックス
-
イベント・活動
能登半島復興チャリティイベント 「つなぐのと〜あなたは尊い〜」のご案内
2024/04/11
能登半島復興チャリティイベント 「つなぐのと〜あなたは尊い〜」を 石川県羽咋市、本山妙成寺…
-
お知らせ
2024/01/21
能登半島地震の寄付金 支援金 52件 4,808,943円 義援金 6件 540,260…
-
ブログ
2024/01/18
平成7年1月17日朝5時46分、淡路島北部を震源とする大地震が発生しました。のちに阪神淡路大…
-
お知らせ
2024/01/15
■1月7日(日) 石川2部青年会の大森上人、高野上人とオンラインにて現状報告と今後の支援につ…
-
お知らせ
2024/01/06
全国日蓮宗青年会では、令和6年1月に発生した能登半島地震において支援金の寄付を受け付けており…
-
お知らせ
2024/01/05
本日(5日)、会長と共に石川県奥能登地域に現地入りすべく調整をしていましたが、報道内容や被災…
| 正式名称 | 全国日蓮宗青年会(ぜんこくにちれんしゅうせいねんかい) |
|---|---|
| メールアドレス | zennissei7634@gmail.com |
| https://twitter.com/zennissei_ | |
| https://www.facebook.com/zennissei | |
| https://www.instagram.com/zennissei/ | |
| LINE 寺院アカウント | https://lin.ee/RwEdIYw |








